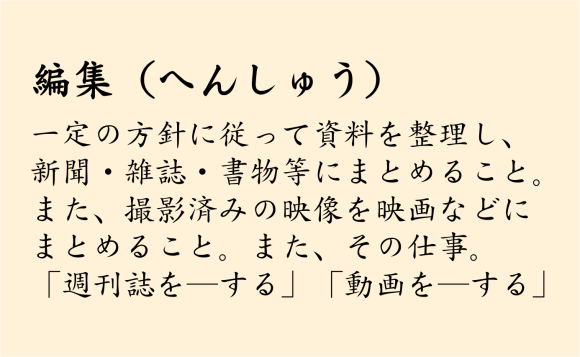編集とは、編集者とは何か。
2017/04/21
ぼくがコピーライターでありながら、旅ライターの仕事をはじめたとき、何人かのWebメディアの編集長から仕事の依頼をいただいた。
とはいえ、「この場所を旅してこんな記事を書いてくれ」と頼まれることは少ない。旅の企画は自分で立てる。行きたい場所、会いたい人を思い浮かべて提案するのだ。
企画書を見た「編集長」がGOを出せば、実際に旅をさせてもらえる。そして、原稿を書いて渡す。編集長は原稿を最初に読んで赤字をいれる。ぼくはその意図をくんで修正をして納品する。
「編集長」って何者なんだろう?
ぼくは疑問に思いはじめた。Webメディアの編集長には、紙と違って「ウン十年のキャリアがあります」なんて人は少ない。同じライターでありながら、肩書き的には「編集者です」と名乗っている人も多い気がする。
書けること。企画できること。構成できること。それが編集長?
それなら、ぼくもコピーライターとしてやってきた。コピーライターは「構成案」というものをつくる。ひとつの冊子のコンセプトを企画して、ページ構成や紙面構成、具体的にいえば、1ページ内の見出しの位置や、各ブロックの文字数や配置もふくめてパワーポイントで「デザイン」するのだ。とはいえ、正確にはデザインではなく設計図である。最終的にはそれをデザイナーに渡して、よりよい紙面にデザインしてもらう。
そうしたことが編集長である条件であるなら、編集長ってコピーライターと変わらないじゃん。ぼくはそう思った。同世代のWebメディア業界の人たちに話を持ちかけてみても、「それなら編集者もコピーライターも一緒かもね」と言う。なぁんだ、と思いながらも、しっくりこない感覚があった。
しかし、紙メディアの雑誌「Spectater」を読んだときに違和感が走った。やっぱり編集ってそんな簡単なものじゃない気がするぞ、と。「髪とワタシ」という雑誌をつくっているミネさんを見ていても何かが違う。ひとつのメディアを立ち上げるとはひとつの人格を立ち上げること。企画とか構成とか表層的でテクニカルなことではなく、深層的で哲学的ななにかがある。
そして、SWITCHの「ほぼ糸井重里」を読んで思った。これが編集という行為なのか、と。
SWITCHの編集長は新井敏記さん。沢木耕太郎に傾倒しているぼくは、沢木氏の仕事に新井氏が深く関わっているらしきことで名前だけは知っていた。
なんでも新井さんは、若いころに「ローリングストーン」というタブロイド雑誌を読んで衝撃を受けたそう。
「若い編集長がインタビューを熱心にしている。インタビューでここまで感動させられるのか。インタビューという形式なら自分もやれるかもしれない、アマチュアでもプロに対抗できる手段だと学んだ」
なるほど、インタビューというのは、まだ何者でもない編集者にとっては有効な手段。語るべきことを持たない若者でも、インタビューをさせていただく相手のお言葉を借りて紙面を成立させることができる。
それだけじゃない。そう気付いたのは「人、旅に出る: Switchインタビュー傑作選」を読んでみたとき。どうやら新井さんにとって一番の得意分野は「旅」だったようだ。だから、インタビューさせていただく相手と一緒に旅に出る。旅をしながらインタビューをする。
アウトプットもまた対談式ではない。旅の途中、取材対象がどんな場面でその言葉を発したのか。その背景を含めて情緒的に描かれている。まるで、小説のように? いや、そうじゃない。ひとつのノンフィクション作品のようだった。
おそらくは沢木氏の影響を受けたのだろう。「一瞬の夏」のように、取材対象に自らが巻きこまれにいくことで一人称を獲得する。そんなニュージャーナリズムの影響が色濃く出ている。つまり、新井さん自身が語り手となり自らが体験した旅を書く。それがインタビュー記事として成立しているのだ。
最近のSWITCHは残念ながら、普通の雑誌に近づいていているようにも思えるが、昔のSWITCHは「旅のにおい」が、強いては「新井さんのにおい」が、全ページを通じてもっと濃かったように思う。そして、それはSWITCHをSWITCHたらしめるブランドであり、哲学だった。
編集とはなにか。それは、そのメディアにしかない「におい」を持たせること。それを1ページの隙もなく充満させること、なのかもしれない。ひとりで書いているうちは簡単かもしれない。しかし、それを大所帯になっても貫けるか。ライターやカメラマンを増やしても、「多様性を受け入れる」なんて言葉で逃げずに、同じにおいを持たせることができるか。その戦いを続けている人を編集者というのではないだろうか。
「広告掲載ゼロからはじまったのですが、雑誌を続けていると、こういう広告がほしいなという気持ちが出てきます。おもねるというよりは、それが目標になるんです。だから、雑誌に載せたい広告のクライアントに自分たちで勝手に営業をかけようと思いました」
なるほど、こうして雑誌で食べていけるようにすることも編集者の仕事だろう。しかし、糸井さんとの対談の中にはこんな言葉もあった。
「やりたいからやる、が第一義。これが売れるからやる、ではなく。やりたいからやる。なんなら儲かるぜ。」
大企業病のようなものだが、食べることに迎合すると雑誌は死んでしまう。大きな雑誌は宿命的にこれに陥っているように思う。しかし、だからこそ、無名の個人がメディア業界に参入していくチャンスが残されている。
そして、最後にこれは糸井さんの言葉だったように思うが、耳が痛い言葉をメモ。
「インタビューができるつもりがいちばんつまらないところにいく。飛び抜けて得意か、あるいは、まったくできませんがなんとか友達になってみようと思いますという人」
これは本当に刺さった。ぼくはインタビューが得意でも何者でもないくせに、理論武装してなんとか相手と対等に話をしようと気構えてしまう。そして失敗する。もっと素直に友達になってみようとすること。まずはそこからなのだ。