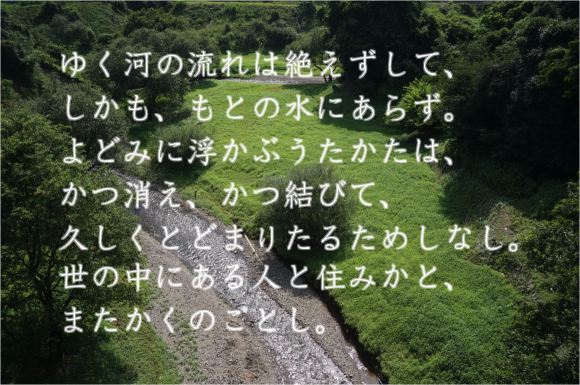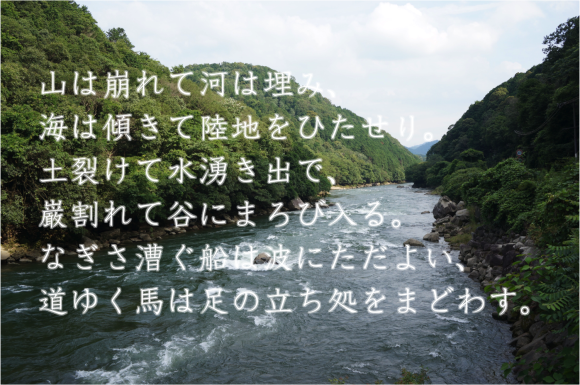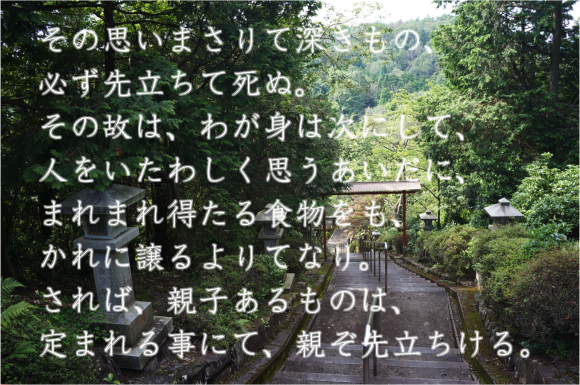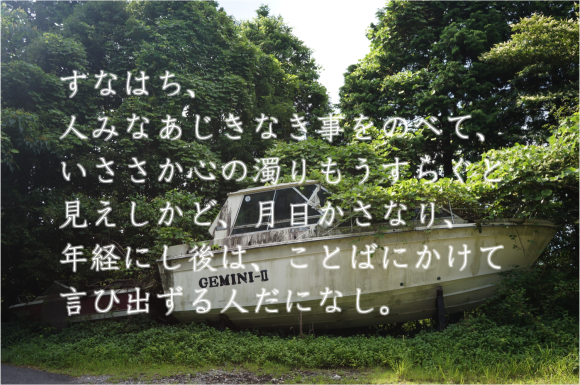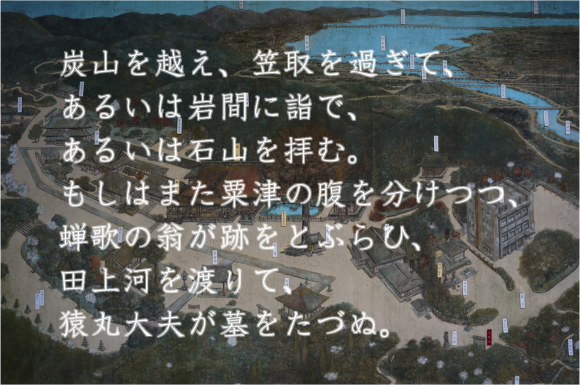【旅訳:方丈記】元祖ミニマリスト 鴨長明の人生をたどる旅(後編)
「方丈」とは「四畳半」のような意味であり、その家は折り畳み式のモバイルハウス。その暮らしに辿り着くまでに、鴨長明がいかなる人生を歩んできたかを前編で書いてきた。
しかし、方丈記では自らの人生についてほとんど触れられていない。
方丈記は亡くなる直前に書かれたものだが、長明が地震や火事などの災害を目の当たりにしてきた経験から、大きな家を所有するためにあくせく働いて心を悩ませるのは人生の無駄遣い。最小限の物と住まいで、好きなことを自由にやってこそ人生だ。そう説いているのが方丈記である。
わずか1万字ほどの短編で、音読しても1時間もあれば読み終えてしまう。しかも、和歌で鍛えた一行はキャッチコピーのようでもあり、それを紐解いていく構成は「日記」ではなく、読み手を説得するための「コピーライティング」に近いものがある。
この旅では、作中に書かれている場所を訪ねながら、方丈記を読んでみたいと思う。
●第1章:人も住まいもすべては変化し続ける
口の中で飴玉を舐めるように言葉を転がしてみてほしい。日本人としてのDNAが古文を解凍してくれるのか、「川の流れがそうであるように、すべては絶えず変化する。人間にも住まいにも永遠なんてないことを知っておくべきだ」そんな意味が時空を超えて伝わってくる。
続く文章で、「京の都で60年経っても同じ家に住んでいる人は20人に1人だ」と長明は言う。今でも都会の店や人の移り変わりの速さは似たようなものではないだろうか。そこで彼はすべての哲学者が行き当たる問いを投げかける。
生まれて死んでの繰り返し。人はどこから来てどこへ行くというのか。
何のために生きるのか、と人生の意味を問いかけるところまでが第1章。長明は自分の人生を振り返りつつ、この難題に答えようとする。
●第2章:地震、火事、人災……それでも人は忘れてしまう
迫り来る対句は音楽のように鳴り響き、瞼を閉じずともその光景が目に浮かぶ。これは当時マグニチュード7.4と言われた元暦の大地震の描写である。第2章では、火事、竜巻、飢饉、遷都など、長明が実際に体験してきた災害についてジャーナリスティックな視点で描かれる。
火事や竜巻では金銀財宝や家を所有することの儚さを、飢饉では食物を田舎に依存している都会の危うさを、遷都では転勤で家が無価値になる切なさを説いているが、極めて厳密なノンフィクション。
一貫して自分の目で見た事実を書く姿勢には、「なんでも見てやろう」と現場に足を運び、自分の足を動かしてきた長明の息づかいが伝わってくる。たとえば、こんな話がある。
極限状態においても、親は自分の子どもに食べ物を譲ろうとする。だから決まって親が先に死んでしまう。あわれなことに、母親が死んだことに気づかずに、そのおっぱいを吸い続ける赤ちゃんの姿があった、との話である。こうしたエピソードが語られたあとに、こう続く。
人間なんてちっぽけなものだ、これからは慎ましく生きよう、地震が起きたばかりの頃はそう言っているけど、月日が経つとみんな忘れてしまう。
長明は800年前にこう言い残しているわけだが、現代に生きる僕らにとっては耳が痛い話である。
この章は、方丈記全体の約半分を占める。長明は度重なる災害を目の当たりにしてきた結果、立派な家を建てるために生きるなんて無意味である、と言うのである。そして、残り半分をかけて、いかに生きるべきかを語りはじめる。これまでたっぷりと感情移入させられているだけに、乾いた喉を潤すような説得力があるのだが、まさしくボディコピーのような構成だと僕は思う。
●第3章:よけいなものを捨てれば自由になれる
奇しくも、東日本大震災後に話題となった「ミニマリスト」と同じ思考である。寝泊りするのに充分な家と、好きなことをやるための物だけあればいい。長明が実践した四畳半の家は解体も組立ても簡単。いつでも引越しができるモバイルハウスだった。そのスペックについては「鴨長明が作った800年前のモバイルハウスとは」に書いた。
その暮らしぶりは、よほど充実していたと見える。
花鳥風月を友として、春夏秋冬の自然を味わう。粗食に慣れるとなんでもない食べ物がおいしく感じられるし、人目を気にして衣服にこだわる必要もない。おまけに、念仏だって適当にサボってもバレない。ここにはめんどくさい規制もなければ、とやかく言う人もいない。好きな和歌を好きなだけ詠い、琵琶だって好きなだけ奏でられる。ここだけの話、うたた寝こそが最高の幸せだと思うのですよ……などなど、文章はノリにノッている。筆が止まらないとはこのことだ。
ときに、近所の子どもが遊びに来るという記述もある。
世捨て人のようにも思われているかもしれないが、長明が隠居した日野南山から都まで歩いて3時間。現代の東京で言えば、多摩や湘南に住む感覚ではないだろうか。都心との距離を保ちつつ、自然に近い静かな場所で心豊かに生きる。長明が伝えたいのはそういう暮らしなのだと思う。
欲をかかずにあくせく働かない。穏やかに暮らすことだけを望めば、心配事もなくなるだろう。
人に雇われる人間は、給与や待遇のいいことばかりを期待して、穏やかな暮らしを忘れてしまっている。だったら、雇うのも雇われるのもまっぴらだ。ぜんぶ、自分でやればいいのだ。それによって疲れることもあるかもしれないが、他人に気を遣うより楽である。
あまりに現代を言い表していて驚かされるが、これも長明が書いていることである。国家公務員として宮廷で働いたことがある彼ならではの本音だろう。
現代でも「お金とは何か」を考えずに「金持ちになりたい」と言う人がいる。長明の言葉を借りると、お金があると「他者の時間」を使うことができる。たとえば、デザイナー住宅のような家に住もうと思ったら、たくさんの人を動かすことになり、たくさんのお金が必要になる。
「お金を持つ」という本質的な意味は、人間が持つ平等の資産である「時間」を、他人のぶんまで自分のものとして使えるということなのだ。だったら、はじめから「自分の時間」をお金に変換せずに、自分の時間は自分で使ったほうがいい。僕にはそう言っているようにも聞こえる。
少なくとも長明は「牛車に乗るより、自分の足で歩くほうがいい」と書いている。「そのほうが健康になるでしょ」とユーモアを交えながら。
●続:鴨長明の人生をたどる旅
方丈記の中には、自由気ままな暮らしとしてこのような文章もある。
岩間寺、石山寺、蝉丸神社、猿丸神社。800年前の方丈記に書かれている場所が今も残っている。これまでの写真は、それらを訪ねる途中に撮った景色だが、自分が歩いている場所を、長明も歩いていたと思うと不思議と嬉しくなるものである。
「暇つぶしに歩いて山を越えて寺をめぐり、帰り道に山菜を摘んで帰った。」長明はそう簡単に書いているが信じられない健脚である。
しかも、長明は57歳にして「鎌倉」まで歩いている。時の大将軍であり、歌人としても名を馳せていた「源実朝」に会いに行ったのだ。その後、京都に戻って書き上げたのが「方丈記」。立て続けに「無名抄」、「発心集」と名作を完成させて62歳で亡くなった。大往生と言うほかない。
「物を持たずに、人と比べずに、自分がやりたいことを自由にやることこそが幸せなんだ。」
方丈記で鴨長明が伝えたかったことは、この一点に尽きると僕は思っている。
人も住まいも絶えず変化する。家にお金をかけてもいつ壊れるかわからない。「あの地震を忘れない」ということは、「変わらないものなどない」ということを忘れないことでもある。
バブルの時代は知らないが、時代は常に変わり続けている。家は新築で建てるもの、車は買い換えるもの、そう考える人は減っているかもしれないが、ローンを使うような買い物をする、そのために自分がやりたいことまで我慢して働いている、なんてことがあったら本末転倒。立ち止まって、方丈記を読んでみてもいいのかもしれない。
●第4章:方丈記には続きがある
起承転結の「結」にあたる第4章。それは原稿用紙1枚ほどの短い文章である。ここが方丈記最大のミステリーであり、解釈が分かれるところである。
これまで「自由な暮らし最高!」と散々言っておきながら急転直下。「出家した身としては執着を捨てなければいけないのに、自分は“自由な暮らしをする”ということに執着しているとも言える」と、反省の弁を見せるのだ。
そして、「最後の一行」をこう締める。
「修行不足の身で偉そうに言ってしまって申し訳ない。私めは念仏を唱えて筆を置くことにする。」
そういう説もある。しかし、果たしてそうだろうか。僕は反語であり皮肉であると思う。
「テキトーに南無阿弥陀仏と3回唱えてハイ、終了!」
最後の歌詞と同時に演奏が鳴り止むロックンロール。僕にはまるでそう聞こえる。
思うに、どれだけ長明が言葉を尽くして説明しても、「ひとりぼっちで山に引きこもって何が楽しいのか」そう言って聞く耳を持たない人が多かったのではないだろうか。
変わることを恐れる人は、「自分にはできない」と言って耳を塞ごうとする。もしかすると、鎌倉まで会いに行った源実朝にも理解してもらえなかったのかもしれない。この最後の一行は、分かってもらえない人に対するアンチテーゼであり、ミステリーではなくヒステリーではないだろうか。
世の中の言いなりになっていると、窮屈な思いをする。かと言って、それに従わなければ狂人あつかいだ。
これは第3章にある一節だが、「人と違う道を歩む者はいつだって狂人と呼ばれる。だが恐れるな。」僕にはそう言っているように聞こえてならない。前編のような旅をして長明の人生を思い描いてみるとなおさらそう思う。
長明は出家した自分の立場を計算して、禁書にならぬよう絶妙な言い回しで書き上げた。その「最後の一行」で、自分の本当の気持ちを暗に伝えようとした。そもそも方丈記全体で炎上を避けるような慎重な言葉使いが見られるのだが、それらも含めて絶妙なコピーライティングではないかと思うのだ。
最後の一行を、あなたはどう読むだろうか。あらかじめ方丈記を読んだ上で、鴨長明の人生をたどる旅をする。そして、もう一度、方丈記を読んでみる。そうして、自分の目で確かめてみてほしいと思う。